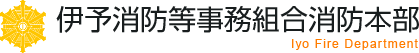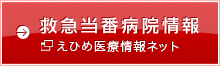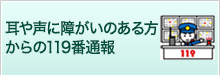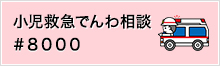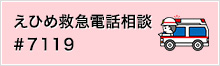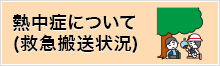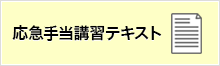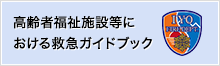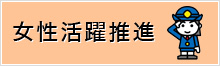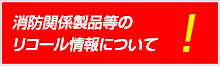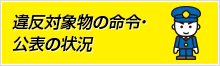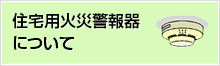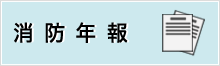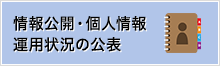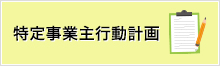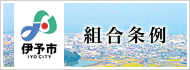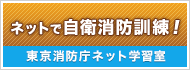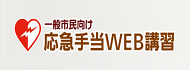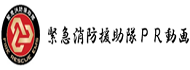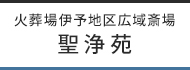消防豆知識 | 一覧
全国火災予防運動の始まり
投稿日:2013年2月14日
全国火災予防運動が始まったきっかけは、昭和2年3月7日に、丹後西北部を襲ったマグニチュード7.5の「北丹後地震」でした。
北丹後地震から3年後に、第1回の防火運動が近畿地方で実施されました。京都、大阪、兵庫、滋賀および奈良の二府三県が参加し、実施要綱を定めて火災予防に関する講習やラジオによる広報を行ったほか、小学校での火災予防の講話、さらには消防職員や警察職員による消防演習などが、盛大に行われました。
開始当初は、1日だけの活動でしたが、終戦の年の昭和20年に、GHQ(連合軍総司令部)の指示により、10月21日から27日までの一週間を、全国一斉の火災予防運動として行いました。これが、火災予防運動を一週間として行った始まりです。
救急現場のエキスパート救急救命士
投稿日:2013年2月14日
「救急救命士」は、厚生労働大臣の免許による医療従事者で、平成3年に制定された国家資格です。救急現場での応急処置の充実と救命率の向上を目的に設けられました。救急救命士は心肺停止状態の傷病者に対して、医師の指示のもとに、器具を用いた気道確保や静脈路確保のための輸液などの「救急救命処置」を行うことができます。
また近年、救急救命処置の範囲が拡大され、県のメディカルコントロール協議会の認定を受けた救急救命士は、「気管挿管」や「薬剤(エピネフリン)投与」を行うことができるようになりました。

救急救命士ワッペン
消防自動車の色
投稿日:2013年2月14日


緊急自動車を赤や白に塗色しているのは、色彩が持つ人間の感覚に訴える効果を狙うことがもとになっています。
では、消防車は、なぜ赤色なのでしょうか・・・?
理由は定かではありませんが、外国から輸入した蒸気ポンプや消防車が赤色であったため日本も同じ色にしたということが一般的な理由のようです。
なお、昭和26年に「道路運送車両の保安基準」という運輸省令で、「緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車にあっては白色とする」と定められました。
一般的に消防車は赤色と言われていますが、法規上では「朱色」なのです。
救急車の場合は、その他の緊急自動車に分類されるため、白の塗色に赤色の一線が入っています。
外国の消防車の塗色ですが、フランス、イギリス、オーストリア等では赤色。ドイツでは、赤又は紫色。アメリカでは赤、白、黄、青、黒色など消防局によって色が異なるようです。